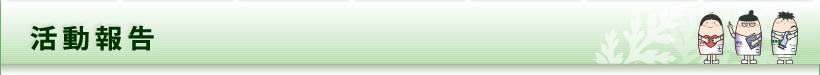平成25年度京都府立医科大学看護研究会に参加してきました!
大雪による交通機関のトラブルにより、急遽岡山経由の新幹線で京都に向かいました。出発のばたばたから6時間かけようやく到着しましたが、最初の文部科学省口頭教育局医学教育課大学病院支援室 専門官の市村先生の基調講演は拝聴することができませんでした。内容は、「看護職人材育成の現状と課題」でした。文科省がGP事業を開始した背景や現状と課題についてのお話をされました。また、GP事業の平成21年度採択8校は今年で終了、残り4校も次年度で終了しますが、この成果を踏まえ、新たなGP事業が計画されており、これについて説明されていました。次期GPは、大学病院と自大学看護部の連携を基盤として訪問看護ステーションや介護・福祉の現場で看護に従事する看護職とも連携し、「患者の地域での暮らしや看取りを見据えた看護が提供できる看護師を要請すること」が目的の事業であります。今後の日本の超高齢化社会に向けて大学病院看護職の在り方がとわれていくものと思われます。
シンポジウムでは、「看護職人材育成ネットワーク」というテーマで行われ、京都府立医科大学附属病院副病院長兼看護部長の小城智圭子氏より「看護実践キャリア開発センターの課題と展望と題し、 「循環型教育システムによる看護師育成プラン」の概要の説明がありました。教育プログラムには複数のプログラムがあり、①一人前看護師育成プログラムでは、当院が対人援助向上プログラムの中で問題解決能力・倫理的感受性・コミュニケーション能力の3つの視点から組み立てられているのに対し、看護実践(薬剤治療、医療機器、集中ケア、救急看護、複数ケア、夜勤対応、情報活用)・組織的役割遂行・教育研究としての3側面から構成されていました。②中堅達人キャリアアッププログラムではジェネラリストとして質の高い看護サービスを提供できる看護職育成する。③復帰支援プログラムでは、ランチョンセミナーなどを開催し実際に復職した先輩看護師の情報を聞けるような場を提供しているとのことでありました。5年間の成果として、看護学科と看護部との連携による教育システムができたこと、教育では公開講座を充実し地域貢献できた点を強調されていました。地域のニーズの高さを改めて感じたとのことであり、看護協会や行政との連携も視野に入れていく必要があると結んでいました。なお、このGP事業は次年度以降も大学予算を確保し継続していくとのことでした。他には、学校法人東京女子医科大学看護職キャリア開発支援センター長 川野良子氏より「看護職キャリア開発支援センターにおける人材育成」、東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科助教 川本祐子氏による「看護職人材育成に向けた医療機関と養成機関の連携における課題や展望」、京都府看護協会会長 今西美津恵氏による 「継続教育における京都府看護協会の役割とその実際」の報告がありました。
東京女子医大のようにGP事業に採択されていない大学もそれぞれに、プロジェクトを立ち上げ継続教育、人材育成に取り組んでおり、地域貢献も効果的に実施していることがわかり参考になりました。また学生や新人看護師のメンタルヘルス上の問題が多い昨今、看護学生の教育に現場の看護師が関わることで、学生のレディネスの質が上がり、それが不安の軽減にも繋がり、臨床にスムーズに入れるのではないかと思いました。保健学科との人事交流のあり方を更に検討していく必要を感じました。
会場では、午前中教育委員会等で取り組んだ新人看護師への指導の実践報告や同病院スタッフによる研究発表が行われておりポスターが貼られていました。
- H23.11文部科学省「看護師の人材養成システムの確立」ネットワーク強化会議・公開フォーラムに参加しました! (2011年11月8日)
- 第1回看護師長グループワーク開催 (2011年11月1日)
- 第1回キャリア支援委員会グループワーク開催 (2011年11月1日)
- 第1回キャリア支援委員会研修開催 (2011年11月1日)
- 平成22年度報告書発行!! (2011年10月31日)
- 第1回キャリアサロンを開催しました (2011年9月15日)
- 平成23年度看護学専攻FD研修会開催 (2011年9月13日)
- 教育担当者受入れプログラムの中間カンファレンスを開催 (2011年9月8日)
- 教育担当者育成研修「動機づけるスキル」 (2011年8月25日)
- 医学教育セミナー&ワークショップ参加 in 岐阜大学医学部 (2011年8月15日)